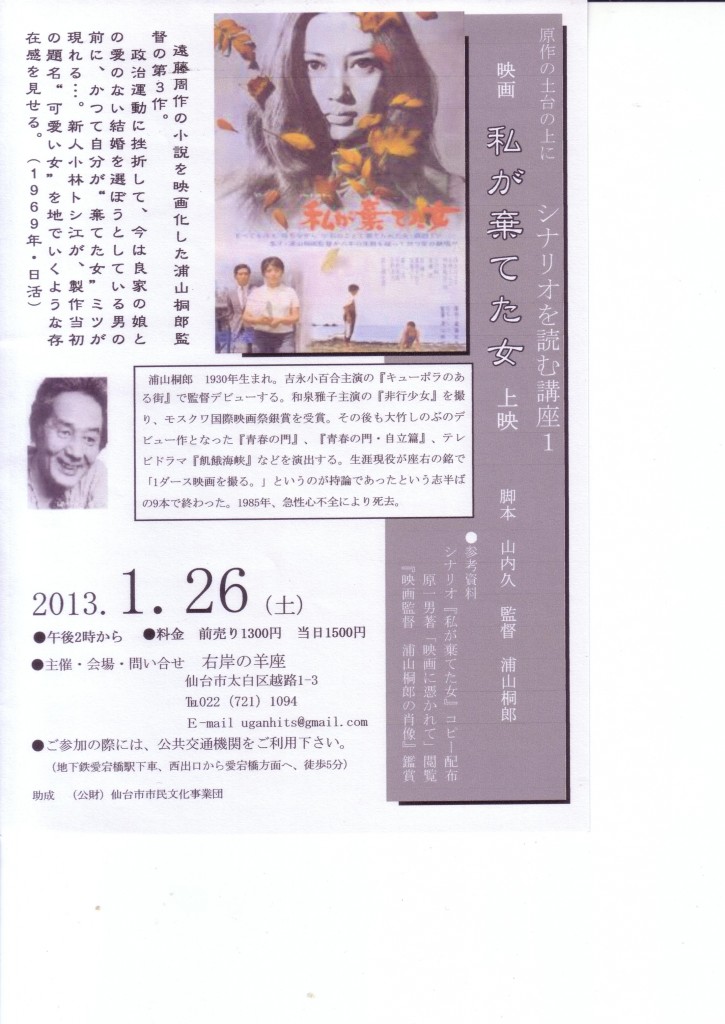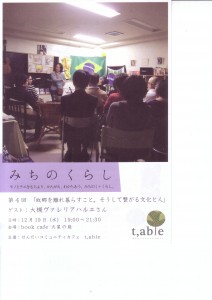青池憲司監督トーク
「私のドキュメンタリー映画遍歴」(破の巻)
2012年9月30日 @右岸の羊座
【口上】
おのれが喋ったことを文字にして読みかえすと、いやはや、これはこれは・・・という気分になってきます。そこですこしばかり手をくわえて体裁を整えようとするのですが、これがまた一筋縄ではいきません。ままよ、喋ったことは喋ったことだ、と以下第2回「破」の巻、いかなることにあいなりますか。
■映画が「第3の道」だと直感した
さて、僕は1970年に再び上京します。はっきりした目標を持たぬまま、ふらっと東京へ出て行きました。東京で何をしようかなと思って、ああそうだ、映画の仕事というのもいいかなと、またしても無謀にも思ったわけです。なぜ映画の仕事かというと、60年代を生活しながら生きてきて、いろんな社会的な運動に参加した経験が自然に背中を押したような格好でした。
当時はベトナム反戦にしても、大学解体の全共闘運動にしても、結構政治闘争の色合いが強かったわけです。政治闘争というのは、党派がいろいろあります。中でも一番メジャーなのは日本共産党や社会党であるわけですが、当時は、そうした既成左翼を否定する全学連のいろんな党派がありました。
そうした党派(新左翼)は、社会の支持を受けて自分たちの運動が盛り上がっている間はいいのですが、うまくいかなくて下り坂になってくると、互いに足の引っ張り合いをするわけです。政治闘争は白か黒か、右か左かの二者択一になりがちです。そういう選択肢しかないのが嫌だなという気持ちが僕にはありました。右でも左でもない第3の道をなぜ選べないのかと思い悩んでいたのです。そして、映画作りなら、もっといろんな価値をふくみこんだ第3の選択肢になり得るはずだと、非常に乱暴な論理だったのかもしれませんが、僕にはそういう確信があったのです。
■30歳から監督を志した2人
それで土本典昭さんのところへ行って、実は映画をやりたいのだけれど、どこか紹介してくれませんかと言ったら、土本典昭さんは、ちょっと間を置いてから「お前、幾つになった」と聞いてきました。そのとき僕は30歳でしたが、30歳から映画を始めるなどというやつはまずいないわけです。普通はもっとずっと早い。当時の風潮では、大学時代から撮影所にアルバイトに行き、あるいは製作プロダクションのバイトなどを経験して、そのまま映画の世界に入るのが一つの道でした。だから20代の初めくらいから映画の社会で活躍し、優秀なやつなら28、29歳で監督作品を撮るという時代でしたから。
「やめておいたほうがいいよ」と、土本さんははっきり言いました。封建的とまではいかなくても、古いしきたりがあるのが、まだそのころの映画の世界でしたから。映画作品の中でこそ民主主義とか、非常に開放的な社会や人間、イデオロギーを表現しながら、映画作りの現場の実態は、監督を頂点にした縦構造のヒエラルキーそのものという雰囲気もありました。僕が30歳でそういう世界に入って、仮に助監督をやったとしても、「18、19歳のガキと同じように使いっパシリから始めるなんてできないだろう」と、土本さんは気遣ってくれたのです。
僕は、「パシリばかりでは嫌ですが、そういうことがあっても、やってみたいとは思います」と正直な気持ちを口にしました。すると土本さんは、いきなり「そうか」と言って大きな声で笑うのです。そして、「実は、俺も映画の世界に入ったのは30歳のときさ」と、言うわけです。あのときの驚き、そして目の前がぱっと開けてくるような思いは、ちょっと忘れられません。
土本さんのことをもう少しお話ししますと、日本がアジア太平洋戦争に負けて、いろんなところで民主化が叫ばれた時代に、大学に全学連が結成されたのです(1948年)。彼は全学連の初代副委員長なのです。初代の委員長は武井昭夫さん。後に文芸評論家として、また、新日本文学会の芸術運動家として活動されています。東大の武井さんが全学連の委員長。土本さんは早稲田で副委員長。そういう体制で戦後の学生運動のある時期をずっと引っ張ってきた時代があったのです。
■『やさしいにっぽん人』のスタッフに
土本さんは、政治に直接かかわった時期を経て、その世界を離れ、べつの何かをやろうかと考えたときに、映画の世界を選択するわけです。彼のようなすぐれた映画監督と僕をくらべるつもりはまったくありませんが、30歳から映画を始めたという共通点があったことを、そのときに初めて知ったのです。
僕が30歳で映画の世界に入ったそのときに、土本さんが準備中だった作品が、水俣シリーズの第1作、『水俣 患者さんとその世界』でした。僕には、あわよくば、その土本作品のスタッフになろうという下心があったのですが、残念ながらそのときにはスタッフ編成が全部終っていて、入り込めませんでした。
しかし、同じ東プロダクションで東陽一監督が劇映画を準備していて、その作品のスタッフにと、土本さんは紹介してくれた。それで東陽一監督のスタッフに製作進行という役割でついたのが、僕の実作者としての映画世界の第一歩でした。『やさしいにっぽん人』というタイトルで、河原崎長一郎さんと緑魔子さんの主演作品です。
土本作品『水俣 患者さんとその世界』の撮影助手が一之瀬正史さんで、その後、おたがいに一本立ちして映画を撮るようになり、今回も石巻でいっしょに映画を作りました。『3月11日を生きて〜石巻・門脇小・人びと・ことば〜』と『津波のあとの時間割〜石巻・門脇小・1年の記録〜』です。一之瀬さんとはたがいに助手時代の1970年ころから、40年間以上のお付き合いということになります。
■われらの映画館を作ってしまえ
1970年以降、僕は東陽一作品の製作進行と助監督を3本務めました。『やさしいにっぽん人』の次が『日本妖怪伝サトリ』で、これはあまり上映されていない作品です。そして3本目が1978年の『サード』。永島敏行と森下愛子主演の映画。この映画は「キネマ旬報」のその年のベストワンに輝きました。
『やさしいにっぽん人』は内容が優れていたばかりか、劇映画の上映スタイルの点でも画期的でした。当時、ドキュメンタリー映画の場合は、各地で自主上映会が企画されて全国に普及していく回路がありました。しかし、劇映画の上映館は大手が独占していました。劇映画を独立プロダクションが自主製作して自主上映するなどということは、新藤兼人さんや山本薩夫さんなどの独立プロを除けば、あまり考えられなかった時代でした。
東プロダクションが自主制作した『やさしいにっぽん人』の上映をどうするか? 今のようなミニシアターは全くありませんでしたし、アート系の映画館もないわけですから。当時は唯一、アートシアター新宿文化という小屋(映画館)があり、そこで短期間上映されることはあったとしても、『水俣』などドキュメンタリー映画のように広く全国的に見られるという機会は、独立プロの劇映画では皆無でした。
でも当時の僕らは、なんとかして『やさしいにっぽん人』を少しでも多くの人に見てもらいたいと思った。それで、どこも上映してくれないのなら自分たちで映画館を作ってしまえと、バカなことを考えたわけです。映画屋というのはバカなことを考えた途端にすぐに実行してしまいます。僕もその一人として、小屋づくりに猛進したのです。
■高円寺の手作りお座敷映画館
小屋さがしをどうしたか? 70年代には、今と違ってインターネットも検索エンジンもありませんから、東京都の分厚い職業別電話帳を開いて、不動産屋に片端から電話をかけまくるわけです。これこれの適当な物件はないかと、一週間くらい毎日5、6時間ずつ電話をしていたら、あるとき、池袋にいい物件があるというのです。「ただし、あそこは電気が来てないかな」と、その不動産屋は言うのです。
そこは東京拘置所(巣鴨プリズン)でした。今はサンシャインシティになっているところ。あれが昔の東京拘置所のあった場所で、戦争犯罪人などが入っていた施設でした。要するにその不動産屋は、僕らおかしな連中をからかっていたわけです。空き部屋がたくさんあるぞって。からかわれているとは知りながらも、ときにはそんなおふざけがあってもいいかと、こっちも楽しみながら、めげずに電話をかけ続けていました。
やがて、中央線の高円寺駅前に、まだ出来立てのビルが見つかりました。1階から3階まではテナントで埋まっているけれど、地下室ならまだ空いていると。ビルのオーナーは、不動産屋さんの話によれば、「何かやりたい若い連中がいるなら3か月限定で貸してもいい」と、いたって物分かりのいい人だという。見に行くとコンクリートの打ちっ放しで、床もでこぼこしているけれど、僕らに不満があるはずもなく、迷わず契約して小屋(映画館)づくりを始めました。
床のコンクリートを削(はつ)り、椅子を買うお金がないのでの、畳屋さんに古畳を1枚10円で何十枚か払い下げてもらって、それを敷いて客席にしました。畳敷きの映画館です。そして、きっちり4:3の黄金分割のスクリーンを張り、映写室の壁はベニヤ板とベニヤ板の間に畳を挟みました。畳は吸音材にもなるので防音装置の代わりにして映写室を作ったのです。映写機は16ミリを2台備えて、スイッチで切り替える方式。そんな手づくりの映画館を「やさしいにっぽん人劇場 アロンジアロンゾ」と名付けて、僕らは3か月間の興業を開始しました。「アロンジアロンゾallons-y, Alonzo」はゴダールの『気狂いピエロ』に出てくるセリフで、原語はスペイン語、「さあ、いこう!」という意味です。そのころの僕らの気分にぴったりでしたね。 命名は川上皓市キャメラマン(『やさしいにっぽん人』撮影助手)。1971年夏から秋へかけてのことです。
■学生時代の森田芳光短編も上映
3か月の興業成績は10万円くらいの赤字でした。僕らにとって、この結果は予想外の好成績で、皆で喜んだものです。赤字で喜んじゃまずいんですが・・・アロンジアロンゾでは、『やさしいにっぽん人』と『水俣 患者さんとその世界』の2本をメーンにして、他のドキュメンタリー作品もずいぶんやりました。亀井さんの作品をはじめ、戦前から戦後の名だたる作品はほぼ全部やったと思います。
当時は、若いドキュメンタリストの作品は上映する場所がなかったので、そういう作家たちに積極的に声を掛けて作品を集めました。絵画の展覧会で「アンデパンダン」という言葉があります。無審査で、つまり持ってきたものは全部展覧するという意味ですが、僕らは映画でもそれをやろうと、シネマ・アンデパンダン展というキャッチフレーズであちこちに呼び掛け、若い人たちの作品が続々と集まってきたのを覚えています。
その作品の中に一つ、際立って面白い8ミリ作品がありました。十数秒(数十秒?)の短い作品で、ロケットというのでしょうか、女性が首に下げて中に写真を入れるアクセサリーがありますね。それ風の、卵型の女性の写真が静止画でじっと映っているのです。しばらくすると、ふっとフェードアウトしていくのですが、その消えかけた瞬間に画面の外から「お母さん」という声が被ってきます。
これはタイトルが『A Mother』という作品で、中身はそれだけのことなのですが、何とも言えない味わいがあって面白い。仲間たちの間でも上映しながら話題になっていました。これを作ったのは、当時日大芸術学部の森田という学生で、この人が後の森田芳光になるとは、当時はうかがいべくもありませんでした。
そんなふうに、僕が映画の自主製作者になっていったときに、上映場所として自前の小屋(映画館)を作るという発想が湧いたのは、シネクラブ活動のおかげだったと思っていいます。自分自身が見たい映画を見る場所をどうやって確保するのかとやってきた、その経験がふっとよみがえり、映画館でやってくれないのなら自前で小屋を作ってしまえ、みたいな。1971年とはそういう、ちょっと忘れられない年でした。
(「私のドキュメンタリー映画遍歴」破の巻・了)